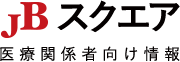どうやってるの?チームで取り組む敗血症診療
-Rapid response systemの活用

札幌医科大学附属病院の取り組み
升田 好樹 先生 札幌医科大学医学部 集中治療医学 教授
はじめに、札幌医科大学附属病院における集中治療部の役割についてお聞かせください。
升田先生:
当院の集中治療部(ICU)は、大きな手術後の患者さんや入院中に重症となった患者さんに対して、集中的に治療・看護を行っています。病床数は、全938床のうちICUは12床です。
ICU開設当初よりclosed
ICUという運営形態を取り、専従の集中治療医が24時間体制でICUに常駐し、診療科主治医と密に連携しながら治療を行っています。朝・夕のカンファレンスには、ICU医師、主治医、看護師、薬剤師、
臨床工学技士、理学療法士など、患者さんの治療に関わる全てのメンバーが参加します。そこで患者さんの治療方針を協議・決定し、チーム医療を行っています。
敗血症早期発見の取り組み
札幌医科大学附属病院のRRSの実際について教えてください。
升田先生: 院内ではMET(Medical emergency team)チームをICUのスタッフを中心に構成しています。METコールの起動基準を決めており、病棟でバイタルサインの異常が生じた際にコールしてもらいMETが起動します。必要に応じて患者さんをICUに搬送します(図1)。コールの対象となった患者さんの約半数は敗血症ないし感染症が絡むケースです。また、病棟では敗血症とは考えられていない患者さんの約半数が敗血症であるという状況です。

一般病棟ではどのような指標を用いてスクリーニングされているのでしょうか?
升田先生:
呼吸数が重要な観察ポイントであると考えています。この呼吸数は指標としては非常にシンプルで、呼吸数が多い場合には、患者さん本人が大丈夫だと言ってもICU搬送を含む治療介入を考慮します。結果的に、重症化しなくて済むケースももちろんありますが、病棟でMETを要請すると判断されたことも踏まえ、はぁはぁと荒い呼吸の場合には、基本的には病棟での厳重なモニタリングやICUで診るようにしています。
一方、ゆっくりした安静な呼吸をしている場合は、病棟でもう少し診ていていいのではと考えることもあり、ここは経験的な判断になります。
以前は、コールを受けた際に、「呼吸数はどうですか?」と聞いても、測定されていないことも多くありました。看護師として、呼吸数が重要なバイタルサインの一つであるということは看護学校で習うと思うのですが、実際の現場では、観察表には血圧(収縮期、拡張期)、心拍数、体温、呼吸数と入っているものの、呼吸数については測定されていないケースも多いのです。
そこで私は、当院の看護師長会議に「1日1回、呼吸数を計ってください」とお願いした経緯があり、かつて院内での測定率は約13%でしたが、現在は90%を越えるようになっています。
アラートを要する呼吸数はどう設定されていますか?またMETコールの要請と、それに対する起動はどの職種が行うのでしょうか?
升田先生:
敗血症を疑う患者さんをスクリーニングするためのツールとしてqSOFA(quick sequential sepsis-related organ
failure)がありますが、呼吸数22回/分がカットオフ値とされています.実際に異常を呈する頻度があまりに多くなるため、当院では、30回/分をアラートの目安にしています。
METコールが起動した場合、日中の場合は医師とICUの看護師とで行くこともありますが、基本、医師1人で対応しています。要請の8割以上は医師によるものですが、その背景には看護師が医師に要請してコールに至るというケースが多くあるようです。これは本来現場の看護師などのメディカルスタッフがコールすべきなのですが、METコールで対応するのが医師であるため、コールの壁が高くなるという事情もあるようです。
しかし、コールが遅れることによって患者さんが不利益を被ることに繋がれば、ある意味それはインシデントであるという気持ちで取り組んでおり、全てを拾い上げることはできないまでも、こうした体制があるという安心感はあるのではないかと思います。コール数は年間約100件で、そのうち半分は感染症絡みで、敗血症がそのなかの1~2割を占めています。
敗血症早期発見における多職種の役割
RRSにおいて各職種はどのような役割を担っているのでしょうか?
升田先生:
敗血症の早期発見・治療において、医師のみならず、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床工学技士、管理栄養士などの多職種による介入は必須です。看護師の働きは重要ですが、それに加え、早期からリハビリテーションが行われる現在、理学療法士の役割も大きいものがあります。理学療法士は患者さんを継続してみているため、昨日とのちょっとした違いなど、変化がよくわかるようです。理学療法士から、「先生、あそこの病棟の〇〇さん、診にいった方がいいですよ」といった連絡が来ることもあります。
そういう意味では、薬剤師もそうですし、臨床工学技士もさまざまな機器のメンテナンスで病棟に来ることもあります。こうした、患者さんと接する機会のある全職種で、しっかりと早期発見の意識を共有できることが重要です。患者さんのご家族や、実習で患者さんについている看護学生からのアラートがあってもいと思います。「多職種で気付こう」がスローガンです。
敗血症が疑われる場合の管理はどのようにされていますか?
升田先生:
対応は、患者さんの状態や希望によって異なります。病状や年齢によりあまり積極的な治療を希望されない場合には、薬剤の選択や用量を提示して、引き続き病棟で管理する場合があります。そうでなければ全力で救命に入っていきます。
その際、病棟での集中治療は、病棟、ICUの双方にとって大変で、特に看護師の負担が大きいため、ICUに移します。結果的に、1泊程度の入室で「大丈夫だったね」ということもありますが、それは許容できます。患者さんが1日入室している間、病棟の看護師や当直医は自分の業務に専念することができ、次の日も仕事がしっかりできます。そういった役割分担ができればいいと考えています。
院内での啓発や教育はどのようにされていますか?
升田先生: 2013年にMETコールを開始した当初は、医師も含め職員全員を対象に、METコール、スタットコールについて研修会を実施しました。自由参加なのですが、皆さん興味を持って聞きに来てくれて、数年間継続して行いました。現在は、年に1~2回、トピックス研修会のような形で実施しています。毎年4月には職員の入れ替わりがありますから、継続することが重要だと思っています。
地域への啓発や発信は、どのようにされていますか?
升田先生:
この2年余りはCOVID-19パンデミック下で何もできなかったのですが、今年初めて、北海道の3つの大学病院を含む、いくつかの病院が中心となって、医師と、重症患者さんをみている集中治療室の看護師による、RRS研究会の開催にこぎつけました。RRSに取り組みたいという看護師さんはたくさんいらっしゃるので、この研究会では具体的な取り組み方を含め、成果や問題を共有しています。そうしたなかで、敗血症の早期発見のシステムを、北海道の病院のなかに広めていきたいと考えています。現場での経験が豊富な医師や看護師を講師に招く勉強会や市民公開講座の開催なども考えており、敗血症をキーワードに情報発信していこうと考えています。
RRSが急性期充実体制加算の対象となった今、RRSを単なるチーム作りに留まらせず、敗血症の早期発見・早期介入に繋がる取り組みとするために、さらなる啓発に取り組んでいかなければならないと改めて思っています。
ご活躍のスタッフにもお話を伺いました。
数馬 聡 先生
札幌医科大学附属病院 集中治療部 講師
RRSにおいて数馬先生はどのような業務にあたっているかお聞かせください。
数馬先生:
札幌医科大学では集中治療部が中心となり、いわゆる”Medical Emergency Team
(MET)”を2013年度から発足させ、RRSの活動を行っております。私は院内の急変対応委員会のメンバーとして、METコール事例の各部署へのフィードバックや、集中治療部内で次へ活かすための症例の振り返りを多職種間で行ってきました。各部署からのMETコールに24時間体制で対応し、必要に応じて看護師とともに患者さんを診察し、集中治療の必要があれば直ちに集中治療室に移送します。
令和3年度のMETコール件数は96件(前年度70件)と、ここ2年間はコロナパンデミックで件数はやや減少しましたが、今年度は再び100件を超えるペースとなっています。一方で、他施設でのMETコールからの集中治療室入室の割合がおおよそ10~20%であることと比較して、当院では76%(前年度83%)とかなり高率に集中治療室に入室していることを考えると、まだまだ重症化しつつある患者さんが病棟で“粘られている”ことも考えられます。当院のMETの起動基準(図1)を院内の医療安全マニュアルにも掲げていますが、これらがいかにシンプルなシステムであったとしても、病棟看護師や医師などのスタッフが気兼ねなくコールしてくれる”spirit”を持ってくれるための啓蒙が極めて重要です。そのためにはコールしてくれたスタッフに対して“こんな軽症なのになんでMETコールしたの?”という態度や発言は厳禁です。“早い段階でコールしてくれてありがとうございます”の気持ちが大切なのです。より早期の治療介入は、患者対応にあたる病棟の負担にもつながり、重症化する以前から集中治療医による介入を可能にし、最終的に患者さんの転帰を良好にすることにつながります。
2021年度からは、RRSの一環としてCritical
Care Outreach
System(CCOS)を集中治療部のチームとして開始しました。これは、電子カルテ上の病棟の経過表からバイタルサインを抽出、早期警告スコア(NEWS)を自動計算し、介入が必要と判断されればチーム自ら一般病棟に出向いて重症度の高い症例を中心に回診を行うシステムであり、コールを受けて起動するというMETのpassiveな部分を補うことができればと期待しています。

敗血症の早期発見にはどのようなことが重要だとお考えですか?
数馬先生: 経験的に言えば、小児診療で言うappearance(見た目)をきっかけに敗血症の発見に至ることもありますが、これには例外もあり経験にも左右されます。早期警告スコア(NEWS)は医療者が普遍的に使用することができ、敗血症の早期発見につながると考えられます。NEWSの中でも呼吸数は重要な観察ポイントであると考えています。呼吸数は最低でも15秒間測定してもらい、4倍して1分間の呼吸数を算出してもらいます。忙しい病棟で長く感じるかもしれませんが、血圧測定の時間などと比較しても15秒で患者さんの異常を察知できるのであれば、簡便であると考えられます。これらの観察は、一般的には患者さんと最も長時間接すると考えられる看護師や、時には理学療法士など多職種への教育が重要です。また、迅速なMETコールのためには主治医への伺いを介することなく、看護師など医療スタッフの直接的な“気づき”からのコールが望まれますので、当院では医療安全部から各部署への周知や定期的な院内勉強会などで繰り返し啓蒙活動を行っています。
RRSに関連して行っている活動はありますか?
数馬先生: FCCS(Fundamental Critical Care Support)コースは、米国集中治療医学会(SCCM)が行っているoff the job training course の一つであり、私もインストラクターとして参加しています。集中治療を専門としない医療スタッフの方々を対象に、講義とスキルステーションからなるコースを開催しています(現在はオンライン開催)。最近では看護師のほか、臨床工学技士、理学療法士や薬剤師の方々の受講が増加してきており、多職種間連携のコンセプトが普及しつつあります。スキルステーションでは、RRSのコンセプトを組み込んだシナリオトレーニングとデブリーフィングのコースがあり、実践さながらのRRSを体得し、学ぶことが可能です。これらは集中治療を行うにあたって当然必要とされる基礎知識ですが、どのような領域においても患者さんの病態を理解するうえで必須とされる知識を習得できると思います。また2022年度の診療報酬改定で急性期充実体制加算が新設され、RRS体制の必要性が示されました。この体制の具体的な案件としてFCCSの受講修了が示されており、今後の動向が注目されています。
石郷 友之 さん
札幌医科大学附属病院 薬剤部
集中治療部における業務についてお聞かせください。
石郷さん:
当院ICU病棟での薬剤師の業務は大きく分けて6つになります。
①回診、カンファレンスへの参加
②薬剤選択や投与量提案
③投与薬剤の効果や副作用のモニタリング
④医師、看護師への情報提供と相談応需
⑤ルート管理
⑥医薬品管理
当院ICUでは、朝・夕の回診、カンファレンスに薬剤師が参加して、必要に応じて薬剤選択や投与量などの提案を行っています。また、薬剤師が回診に参加することで重大な薬物相互作用の発生を未然に回避できるとの報告があるように1)、その場で効果や副作用のモニタリング、投与ルートなどの確認が可能となります。
ICU入室患者さんの多くは全身状態が不安定で腎機能などの変動も大きいため、薬物動態が経時的に変化することがよくあります。そのため、薬剤選択や用法用量については、その後の変化も考慮し、有効性と安全性が担保できるような提案を心掛けています。それでも変化が予想を上回る場合もありますが、当院では平日日勤帯は薬剤師がICU病棟に常駐しているため、適宜状況の変化に合わせて医師と協議し、薬剤の調整や、効果や副作用の継続したモニタリングを行っています。その他にも薬剤師が常駐しているメリットとして、医師や看護師からの相談に対して即座に対応できることが挙げられます。新規開始薬剤がある場合は、配合変化、投与ルートについて事前に薬剤師から情報提供することもありますし、看護師から事前に質問を受けることも多いです。また、使用方法が特殊な薬剤に関しては、事前にオーダー方法を医師に情報提供することで、処方オーダーミスを減らすことができると考えられます2)。ICUでは、緊急で使用する薬剤も多く、不足すると患者さんの不利益が大きいため、在庫の管理は重要で、毎日定数の確認と調整を行っています。また、入室患者さんが使用するであろう薬剤を確認し、在庫が無いものに関しては、事前に準備するといった対応も薬剤師が常駐していることでスムーズに行えます。
集中治療部での経験から、敗血症に対する意識に変化はありますか?
石郷さん:
ICU病棟に配属されるまでは、敗血症の患者さんに関わる機会はほとんど無く、薬剤師としてどのような介入ができるかなどはあまり考えたことがありませんでした。
しかし、ICU病棟に配属されて敗血症の患者さんに関わる中で、普段当たり前と考えていた”有効かつ安全な薬物療法”を提供することがとても難しい反面、薬剤師が薬物療法に貢献できる場面は多いと感じました。
例えば、抗菌薬バンコマイシンの投与設計一つとっても、一般病棟ではガイドライン通りに投与設計していれば概ね予想通りの結果が得られることがほとんどでしたが、ICUに入室するような重症の敗血症患者さんではそう上手くはいきませんでした。
その理由の一つとして、全身状態が不安定で循環動態が変化し薬物動態も変化するため、刻一刻と変化する個々の病態に合わせた薬剤選択や投与量設定が必要となるためです。敗血症の早期では、生体炎症反応やストレスホルモンの分泌によって血管透過性が亢進し、細胞内でも血管内でもない場所(サードスペース)に水分が溜まる状態になるため血中濃度は低値となりやすい状態となりますが、そこから全身状態の改善に合わせて、サードスペースに貯留していた水分が血管内に戻ると血中濃度が上昇するかもしれませんし、尿量が増加(利尿期、refilling)すると薬剤のクリアランスが改善し血中濃度が低下するかもしれません。さらに、急性腎障害などを併発しているとその影響も考慮する必要があります。このように、抗菌薬の投与方法一つをとっても刻一刻と変化する多様な因子を総合的に判断する必要があり、ICU配属当初は、そういった状態の把握と今後の経過を含めたアセスメントに苦労しましたが、重要性についても認識できました。刻一刻と変化する病態の把握と合わせて、タンパク結合率や分布容積、消失半減期などのパラメータ、いわゆる薬剤特性を考慮したアセスメントは薬剤師の専門性を大いに活かせる場だと感じ、“有効かつ安全な薬物療法”を提供するためには必要不可欠であると考えるようになりました。当院では、カンファレンスなどで薬剤師から積極的に情報提供・共有できる環境があり、専門性を活かした介入ができる環境や体制も重要であると思います。
敗血症患者さんの病状変化について、特に気を付けていることがあればお聞かせください。
石郷さん:
刻一刻と変化する病態の把握は”有効かつ安全な薬物療法”を提供するためには必要不可欠であると考えています。
まず、敗血症患者さんのICU入室が決まった時点で患者情報の収集を開始し、医師や看護師が処置をしている間に、これから行われる薬物治療を予測していきます。また、敗血症患者さんでは、急性腎障害の合併や持続透析が開始となる場合もあるため、それらも踏まえて薬剤選択・用法用量を調べるようにしています。加えて、敗血症では、適切な抗菌薬治療を迅速に開始する必要があります。私はICU病棟の他に、感染対策チーム(Infection
Control Team:ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship
Team:AST)も兼任しており、ICU入室時に提出された各種培養のグラム染色の結果なども積極的に検査部で臨床検査技師とともに確認し、抗菌薬の選択や用法用量を提案できるようにしています。その際も患者さんの病態の把握は重要であり、抗菌薬の過少投与を避け、かつ安全に使用できるよう薬剤の分布や移行性なども考慮して抗菌薬の種類や用法用量を設定しています。その後、全身管理と抗菌薬治療を行っても改善に乏しい場合、例えばカテコラミンの量を減らせない場合や、利尿期に入らずプラスバランスが続いている場合などは治療方針を再検討することがあります。その際、薬剤師としては、抗菌薬が過少投与になっていないか、薬剤の移行性の悪い感染症が無いか、カバーの外れている微生物による感染は無いかなどを医師と協議するようにしています。
一方、全身状態が改善し感染症の原因菌が明らかとなった場合は、薬剤師からも積極的に抗菌薬のデエスカレーションを提案しています。しかし、そのタイミングで一般病棟への退出ということも多々あります。その際は一般病棟への引継ぎが不十分で広域抗菌薬が漫然と使用されることを防ぐために、主科の医師との情報共有はもちろんのこと、退出先の病棟薬剤師と状態の経過に加えデエスカレーションや治療期間などについても情報共有し、抗菌薬の適正使用を進められるように注意しています。内服薬についても、ICU入室時にはもともと内服していた薬剤が中止されることが多く、状態に合わせて必要な薬剤を再開していく必要があります。これも薬剤師が積極的にICU医師、主科の医師と協議し適切なタイミングで再開できるよう心掛けています。
以上のように急性期から一般病棟へ退出するまでの病態変化に合わせて薬剤師ができることは多く、いつでも対応できるようアンテナを張り巡らせておくことが重要だと思います。
- Rivkin A et al. J Crit Care. 2011;26:104.e1-6.
- Klopotowska JE et al. Critical Care. 2010, 14:R174.
春名 純平 さん
札幌医科大学医学部 集中治療医学研究員/附属病院 看護部
集中治療部における業務についてお聞かせください。
春名さん:
当院の集中治療室(ICU)では、主に侵襲度の高い手術後の患者さんや、敗血症、呼吸不全、などの重症患者さんが入室して治療を受けています。定期手術の患者さんに対しては、概ねクリニカルパスのような形で術後の観察項目はある程度決まっており、それに準じた観察やケアを行うのが通常業務です。時折、定期手術であっても出血などの合併症が生じ、緊急の対応が必要になることはあります。また、心臓血管外科や緊急手術後の患者さんであれば、循環動態が不安定なことが多く、そういう患者さんに対しては、異常の早期発見、あるいは循環変動の原因を、各種モニターを通して推論しながら、医師とともに管理するのが主な業務かと思います。
一方、敗血症や呼吸不全、多臓器障害などで全身状態が悪い患者さんに関しては、定期手術のような対応では留まりません。気道管理、呼吸、循環、意識、体温、患者さんの苦痛などあらゆる側面からの観察が必要になります。各種パラメータの異常値を理解するのはもちろんですが、異常の原因についても推論し、その対応も求められます。こうした患者さんの多くは、気管挿管され、人工呼吸管理が必要です。人工呼吸中の患者さんはとても苦痛が強く、声を出すことができないので、ストレスも溜まります。ですので、適切な鎮痛や鎮静が必要で、患者さんの苦痛を除去するのは看護師の大きな役割です。また、人工呼吸中の患者さんに対しては、口渇や呼吸困難、不眠、不安などのそのほかの不快感が多くあることが最近報告されています1)。こうした不快感に対しても、看護師は対応しなければなりません。こまめに患者さんに声をかけ、辛い部分がないかなどきめ細かいケアを提供できるように心がけています。
敗血症や呼吸不全の患者さんは、緊急入室となりますので、ICUに入室する時間帯もバラバラです。緊急入室した患者さんに対して、医師がスムーズに診療や処置ができるように、先々を読みながら看護師が準備、介助することが必要です。また、緊急時に使用する薬剤や物品を手早く準備したり、適切に薬剤を投与するなど、いろいろなことを考え、手を動かしながら、患者さんの対応をすることも重要な仕事の一つです。
他の職種と異なるのは、患者さんの家族への対応を密に行わなければならない点だと思います。緊急でICUに入室した患者さんの家族は、突然のことで動揺し、不安がとても強い状況にあります。家族に対して、不安感を取り除けるような対応をしたり、必要な情報を提供したり、患者さんのケアに役立つ情報を引き出す、などの家族への対応は非常に重要な仕事です。最近はコロナの影響で、家族面会ができない状況が続いています。そのため、当院ではオンライン面会や、毎日家族への電話連絡をするなど、家族の対応に力を入れています。
敗血症患者さんの病状変化について、特に気を付けていることがあればお聞かせください。
春名さん:
看護師は、ベッドサイドで患者さんの状態を常に観察しています。敗血症患者さんの病状変化で気をつけているのは、循環や呼吸が不安定な部分です。生体モニターの中でも動脈波形、循環に関連する多くのモニターを駆使しながら、その安定化を図ることを優先します。また、代謝性アシドーシスの代償などからの頻呼吸を認める患者さんが多く、呼吸に関しても安定化を図るために観察を強化します。呼吸に関しては、近年、patient
self-induced lung
injury(P-SILI)と呼ばれる、過大な自発呼吸の害についての報告もあり、敗血症患者さんの人工呼吸中の呼吸様式や非同調などに注意して観察しています2)。他にも、敗血症は意識障害を認める患者さんが多く、せん妄症状もよく見られます。対応として鎮静薬などを用いるのですが、その場合、鎮静薬の影響が残ってしまうため、せん妄症状が改善しているのか悪化しているのかがわからなくなることがよくあります。ですので、患者さんの苦痛緩和や安全を守りつつ、定期的に意識状態の変化を観察することが重要です。
病状変化について、という議論からそれるかもしれませんが、敗血症のような重症患者さんにおいて、その後の身体・精神・認知機能障害、いわゆるPost-intensive care syndrome
(PICS)という現象が問題となっています。ですので、こうした患者さんのQOLを高めるケアが重要と考えています。具体的には、循環や呼吸の生理学的なニーズが満たされた段階で、リハビリテーションができるように理学療法士と連携したり看護師のみでのプランを立て、実施します。また、人工呼吸から早く離脱できるように深鎮静は避けて、浅い鎮静あるいは鎮痛薬のみで管理するような鎮痛鎮静薬の使用の工夫も行いますし、人工呼吸からの離脱が可能かについて、日々評価も行います。先にも申し上げましたが、せん妄になるケースも少なくありません。せん妄を誘発するような薬剤の使用を避けたり、リハビリによって昼夜のリズムを整えるなどのケアは常に必要になります。このように、敗血症患者さんの病期を適切に捉え、それに応じたケアを実践することによって、患者さんのQOLが高められると考えます。
院内でのMETコールは医師からのコールが多いようですが、看護師からのコールが増えるにはどのような取り組みが必要でしょうか。
春名さん:
RRSの成功は医師だけでなく看護師のコールが非常に鍵となります。海外の報告では、入院1000対25件以上のコールがRRSの充実した施設と言われています3)。当院においては、2013年からMET、2017年から脳神経外科医師主導で行っているストロークコールが開始され、これらを合わせると、2021年では入院1000対10.2という状況になっています。RRSのコールは、医師からのコールが多く、看護師が主体となってコールしている件数はまだまだ少ないという現状です。この要因として、2点が考えられます。まず、看護師が重症患者さんを見つけた場合には、METコールより先に主治医に連絡するケースが多いことです。重症患者を見つけたとしても、まずは、主治医の診察を待って、METコールをしようという流れになっていると考えられます。しかし、何らかの理由で主治医の診察が遅れてしまった場合には、重症患者さんへの介入が遅れてしまう可能性があるため、看護師からのMETコールが望ましいと考えられます。2つ目に、当院のMETは他の多くの施設とは異なり、医師主導で行っているため、看護師の中には、ICUに入室するような症例ではないとMETコールに躊躇してしまうという点があります。毎年院内向けのセミナーや看護師教育の中で、MET基準については何度もアナウンスしているところですが、なかなか看護師からのコールが増えないというのが現状です。
これらの改善策として、4点あると考えています。1点目は、院内向けの研修でMETコールの基準について周知することを引き続き行うことがまず重要と考えます。2点目は、各一般病棟に重症化予防や急変について考えるコアナースを設定し、コアナースが中心となって急変や患者さんの重症化を予防するための風土を醸成することが有用と考えます。そして、各病棟で生じた重症患者症例あるいは急変症例を振り返るなどの機会を設け、重症化予防のための意識を高めることが重要と考えます。3点目は、RRS関連のデータを可視化することです。MET症例の予後やその後のQOL等についてデータを蓄積し、それを院内に定期的に周知するなどの取り組みが有用かと考えます。4点目は、METコールやRRS
のコールの先を医師だけでなく、RRSを統括する看護師を設置し、看護師to看護師で相談ができるような体制を作ることが有用ではないかと考えています。ちょっと変だな、と思ったら病棟看護師が気軽に相談できることが大切で、これが、重症患者さんの早期治療につながるのではと考えます。
最後に
春名さん: 敗血症をはじめとした重症患者さんのPICSは非常に問題となっており、それを予防するICU内での取り組みを強化する必要があると考えています。一方で、「重症化しなければ」PICSにもならないとも言えますので、RRSの強化によって、重症化の予防、重症患者さんへの早期介入の機会が増えることが非常に重要と考えます。
- Ashkenazy S et al. Intensive Crit Care Nurs. 2021;64:103016.
- Brochard L et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:438–42.
- Jones DA et al. N Engl J Med. 2011;365:139–46.