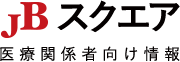どうやってるの?チームで取り組む敗血症診療
-Rapid response systemの活用

【総論】敗血症診療の課題とRRS(Rapid response system)の活用
升田 好樹 先生 札幌医科大学医学部 集中治療医学 教授
敗血症診療における現状と課題
日本において敗血症は増えているのでしょうか?
升田先生:
敗血症は感染症に臓器障害を合併した状態と定義され、その患者数は日本を含め世界中で増えています。日本において最近報告された敗血症に関する初の大規模研究によると、敗血症患者の死亡率は、2010年の約25%から2017年には約18%と減少傾向にあるものの(図1)、入院患者全体に占める敗血症患者の割合は約11万人から約36万人に増え、敗血症による死亡の絶対数も2017年には年間約6万人(1000人あたり年間7.8人[図2])と、2010年に比べ2.3倍となっています1)。
敗血症増加の主な要因は、日米欧などの先進国においては人口の高齢化です。加齢に伴う免疫力低下により感染症に罹患しやすくなることに加え、がんや高血圧、糖尿病などの生活習慣病が増加しており、これらの疾患は若年者よりも高齢者に多いことなどが敗血症増加の背景にあります。
こうした事態を受け、2017年に世界保健機構(WHO)が、敗血症への対策強化のための緊急提言を出しました。この取り組みは医療現場のみに求められているのではなく、政府レベルでの感染症予防のための対策や啓発、治療薬の開発などを含む幅広いものです。
 院内死亡率と平均入院期間の年次変化。院内死亡率:-0.95%/年 [95%CI-1.17%~-0.73%]、R2=0.95、P<0.0001。
院内死亡率と平均入院期間の年次変化。院内死亡率:-0.95%/年 [95%CI-1.17%~-0.73%]、R2=0.95、P<0.0001。入院期間:-1.70日/年 [95%CI-2.21~-1.19]、R2=0.92、P=0.0002。エラーバーは95%CIを示す。CI:信頼区間 対象:2010年~2017年のDPC(包括的評価方式)データより抽出された急性臓器障害を有する重症感染症の成人入院患者
方法:血液培養を採取し抗菌薬投与を行った患者を重症感染症患者として抽出し、そのうち感染症に伴う臓器障害を来した患者を敗血症患者と定義した。そのデータから敗血症患者数、死亡数/死亡率の推移、入院期間などを解析した。 (Imaeda T et al. Crit Care. 2021;25:338-46)
 入院患者1000例あたりの死亡数の年次変化と全入院患者に対する敗血症発症患者の割合。入院患者1000例あたりの死亡数:*1.8/年 [9.5%CI+1.2~+2.3]、R2=0.90、P=0.0003。入院患者全体の敗血症患者の割合:+0.30%/年 [95%CI+0.25%~+0.34%]、R2=0.98、P<0.0001。エラーバーは95%CIを示す。CI:信頼区間
対象:2010年~2017年のDPC(包括的評価方式)データより抽出された急性臓器障害を有する重症感染症の成人入院患者
入院患者1000例あたりの死亡数の年次変化と全入院患者に対する敗血症発症患者の割合。入院患者1000例あたりの死亡数:*1.8/年 [9.5%CI+1.2~+2.3]、R2=0.90、P=0.0003。入院患者全体の敗血症患者の割合:+0.30%/年 [95%CI+0.25%~+0.34%]、R2=0.98、P<0.0001。エラーバーは95%CIを示す。CI:信頼区間
対象:2010年~2017年のDPC(包括的評価方式)データより抽出された急性臓器障害を有する重症感染症の成人入院患者方法:血液培養を採取し抗菌薬投与を行った患者を重症感染症患者として抽出し、そのうち感染症に伴う臓器障害を来した患者を敗血症患者と定義した。そのデータから敗血症患者数、死亡数/死亡率の推移、入院期間などを解析した。 (Imaeda T et al. Crit Care. 2021;25:338-46)
敗血症の診療では現在どのようなことが問題になっているのでしょうか?
升田先生:
病院や老人保健施設などで、入院患者さんや入所されている方が発熱した場合、その時点で既に敗血症がスタートしている可能性があるのです。しかし、その段階で敗血症を疑うということはあまりなく、「ちょっと熱出ちゃったね、様子を見よう」という対応をしがちであるために、重篤な状態になって初めて救急搬送されるという現状があります。
院内において、感染の可能性は、どの診療科にもありますが、敗血症を早期に認知する必要性が、まだ十分には広まっていない現状があり、それが早期発見、早期介入の遅れをもたらしているのです。
敗血症診療を支えるSTS(Sepsis treatment system)とRRS
「敗血症診療ガイドライン2020年版(J-SSCG 2020)」でも推奨されている、STSについて教えてください。
升田先生:
敗血症の多くは集中治療室(ICU)の外で発生しているため、一般病棟や老人保健施設などでも早期に発見し、治療を開始しなければ、重症化した敗血症患者さんを救命することはできません。J-SSCG
20202)には、敗血症を早期に認識・覚知し、適切な体制での診療が受けられることを可能にするためのシステム、STSが新たに追加されました。
STS構築のためには、大きく分けると2方向からの取り組みが必要です。一つは、一般診療をされている施設から敗血症が疑われる患者さんを搬送する際に、適切な診療が可能となる受け入れ先を増やすこと。もう一つは、敗血症を早期発見するための、スクリーニング方法の普及です。
スクリーニングツールとしては早期警告スコア(NEWS)(表1)などがあります。NEWS
では、感染症が疑われる患者において合計スコアが5 点以上、あるいは1項目でも3点以上がある場合、敗血症を疑うことが英国の国民保健サービス(National Health Service:
NHS)により提案されています。
まずはNEWSのようなツールがあることをお伝えし、「怪しいと思ったらとにかく連絡いただければ行きますよ」といった関係の構築でもいいのです。将来的には、患者さんをカメラで撮影し、バイタルサインやX線画像データをリモートで提供してもらえれば、搬送の必要性などの判断ができるようにもなると考えられます。
重症患者さんの搬送に関連して、集中治療学会では2022年3月、「集中治療を要する重症患者の搬送に係る指針」を策定しました3)。これには、重症患者さんの広域搬送の指針として、搬送チーム構成、搬送準備、必要な医療機器および薬剤、搬送時の患者モニタリングなどが示されており、条件を満たせば2022年4月から診療報酬が加算されます。コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにおいて、患者さん搬送の必要性が数多く出たことが指針策定のきっかけとなりましたが、重症患者さんには敗血症も含まれており、こうした指針はSTSの後押しになると考えています。
 (日本版敗血症診療ガイドライン2020 特別委員会. 敗血症診療ガイドライン2020. 日本集中治療医学会雑誌 2021;28:s1-s411)
(日本版敗血症診療ガイドライン2020 特別委員会. 敗血症診療ガイドライン2020. 日本集中治療医学会雑誌 2021;28:s1-s411)
一般病棟で敗血症を疑う患者さんの病状変化に対応するRRSとは、どのような取り組みでしょうか?
升田先生:
RRSは、院内の一般病棟において患者さんの病状変化を早期に認知、介入し、重症化、特に心停止への進展を予防するシステムです。すなわち、病棟にいる具合が悪くなりそうな患者さん、あるいは悪化しているけれど対応できていない患者さんを見つけて情報を共有し、早期に治療に繋ぐための取り組みで、2022年4月から、急性期充実体制加算の要件とされています。
入院患者さんは、さまざまな疾患を持っているために入院されているわけですから、心停止に至ってしまうと、市中で心停止して搬送されてくる方に比べ、回復の可能性は低くなります。このため、心停止以前のもっと早い段階で介入しなければ、救命は難しいと考えられます。心停止後、ないしその直前にアラートが発信され(いわゆるコードブルー)、それに対して始動するチームはたくさんあるのですが、RRSのイメージは、心停止以前の、血圧などバイタルサインの異常に基づく集中治療への連携です。これは現時点ではまだ、十分に普及していないと思います。(図3)
 (升田好樹先生オリジナル)
(升田好樹先生オリジナル)
RRSを構築する上で乗り越えるべき課題とはどのようなことでしょうか?
升田先生:
海外では、入院患者さんのバイタルサインを看護師が測定、あるいは機械的に自動測定して電子カルテに入力し、そのデータをスコア化するシステムが普及しています。スコアが一定の基準に達すると自動的にアラートが出て、主治医ではなく専門チームが駆けつけるのです。こうしたシステムは1990年代から取り入れられており、日本でも採用しているところがあります。
このシステムのポイントは、緊急時に、主治医ではなく専門チームが対応するところです。日本では、患者さんの状態が急変するなどの場合にも、主治医が駆けつけます。しかし、主治医が24時間365日、即座に対応することなど不可能ですから、緊急時において主治医を必須とすることが、対応の遅れをもたらす要因にもなっているのです。現実には、主治医がすべてに対応せざるを得ない状況も一部にはありますが、可能な限りこの現状を変え、RRSを導入することが、医療者、患者さんの双方にとってメリットをもたらすと考えます。
RRSは、自動的にアラートを出して専門チームが駆けつけるのが理想的ですが、チーム編成までいかない場合の現実的な対応として、看護師が主導するパターンと、医師が主導するパターンの2つが考えられます。看護師がトリアージし、必要に応じて専門の医師にコールするパターンが、効率はいいと思います。
STS、RRSの今後の展望についてお聞かせください。
升田先生: 日本では10万人あたりの集中治療室ベッド数が、欧米の10~30床に対し5床と少なく、集中治療専門医も、ベッド数から算出した適正数である4000人に対し半分程度の充足率です4,5)。こうしたなかで、医師のみならず、普段、敗血症治療に関わらない一般病棟の看護師、理学療法士、臨床工学技士、薬剤師、栄養士など、すべてのメディカルスタッフが早期発見ツールを駆使できるようになれば、敗血症への早期介入が可能となり、ひいては患者さんの予後改善に繋がると考えます。全国の施設における、こうした取り組みの拡がりに大いに期待します。
- Imaeda T et al. Crit Care. 2021;25:338-46
- 日本版敗血症診療ガイドライン2020 特別委員会. 敗血症診療ガイドライン2020. 日本集中治療医学会雑誌 2021;28:s1-s411
- 日本集中治療医学会. 集中治療を要する重症患者の搬送に係る指針. 2022年3月23日
https://www.jsicm.org/news/upload/220310JSICM_scyjkhks.pdf - 橋本悟. ICUとCCU 2013;37:113-118
- 内野滋彦. 日集中医誌 2010;17:141-144