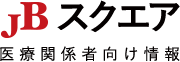どうやってるの?チームで取り組む敗血症診療
-Rapid response systemの活用

RRS、CCOT、ACPに基づくチーム医療
東京ベイ・浦安市川医療センターの取り組み
則末 泰博 先生 東京ベイ・浦安市川医療センター 救急・集中治療科/集中治療部門部長・呼吸器内科部長/センター長補佐
東京ベイ・浦安市川医療センターの取り組み
はじめに、東京ベイ・浦安市川医療センターにおける救急外来の特徴について教えてください。
則末先生:
当院の救急外来部門は、いわゆる欧米型ER(Emergency Room)と呼ばれるシステムを取り入れておりますが、救急外来受診から入院に至る流れが他の欧米型ERを取り入れている施設と異なる面があります。通常、救急外来での初期対応の後は各診療科に患者さんを送りますが、当院では総合診療科(General Internal Medicine; GIM)が、基本的にすべての内科系患者さんの入院を受け入れます。
日本の総合診療科は、通常、診断がつかないケースや、個別専門科の診療範疇に収まらないプロブレムを有するケースの診療にあたる場合が多いと思います。一方、当院のGIMは米国式のGIMです。すなわち、内科系の患者さんは原則としてGIMに入院し、総合診療医が必要に応じて各専門科と共に診療にあたります。このシステムにより、たとえば呼吸不全で救急外来に搬送された患者さんの病態が、循環器に起因するものなのか呼吸器疾患なのか診断がつきにくく、なかなか入院をする診療科が決まらないといった事態を回避することができます。どの科に入院するかは患者さんの問題ではなく、医療システムの問題ですから、そのために救急外来で患者さんが待機状態にならなくても済むという点は、当院の救急外来の重要なポイントだと思います。救急外来部門(ER)、GIM、集中治療部門(ICU)の医師が総合診療医として全般的な知識を有することで、こうしたシステムが可能になっています。
ICUの役割と特徴について教えてください。
則末先生:
当院のICUはGIMの重症バージョンです(図)。米国式のclosed ICUとなっており、基本的にICUの全患者さんに集中治療医が関わって責任を共有します。例えば、心臓血管外科手術後、ICUに入室すると、集中治療医と心臓血管外科医が一緒に診るのですが、治療方針決定後、治療の指示を出したり、患者さんを継続して診るのは集中治療医です。専門科の医師がオーダーしたい場合にはその旨を集中治療医に伝え、集中治療医がオーダーします。すなわちこのシステムでは、同じプランと理解を共有することが絶対条件になるため、患者さんの安全につながり、かつ、医師同士コミュニケーションとチーム医療を良い意味で強制するシステムでもあるわけです。
また、各専門科の医師が病院に当直することはありません。集中治療医が24時間患者さんを診ており、何かあれば初期対応と必要であれば各科への連絡をおこなう事ができるため、循環器内科、心臓血管外科、脳神経外科などを含めて、各専門科の医師はオンコールの状態ではいますが、当直の必要はないのです。これにより、専門医は各科の業務により専念できますし、かつ働き方改革にもなっていると思います。これが、米国では一般的なclosed ICUのシステムです。
当院のICUでは現在、スタッフである集中治療専門医5人と、フェロー、レジデントがいます。
各職種では、ICU専門の看護師、薬剤師がいて、必ず回診についてくれます。病床数は、コロナ感染症への対応で減っている現在、ICUが12床、HCUが10床となっています。
 東京ベイ・浦安市川医療センター 則末泰博先生ご提供
東京ベイ・浦安市川医療センター 則末泰博先生ご提供
集中治療医と専門科医師とのコミュニケーションの実際について教えてください。
則末先生:
当院では、ベッドサイド回診を非常に重視しています。ICUでは朝と夕のベッドサイド回診があり、基本的に朝の回診で重要なことのほとんどが決まります。患者さんの状態を細かくシステムベース(臓器ごと)でチェックし、ICUの医師のプレゼンに対して議論をし、治療方針を決めていきます。
部屋に閉じこもってカルテを供覧しながらおこなうカンファレンスの場合、症例をプレゼンする医師がいるわけですが、その医師のフィルターを通しているため、気づかないことや勘違いがあり得ることは否めません。患者さんの身体所見や見た目の雰囲気、人工呼吸器のモニターのグラフィックなど、オンタイムでみることで得られる情報というのは多くありますが、それらが全て一人の人間を通して伝達されてしまうというのは危ないのです。加えて、タイムラグがあります。朝レジデントやフェローがみた時間から30分経っているだけで全く状況が変わっていることもあります。
ベッドサイドの場合は、その場で診て、必要に応じてさらに情報収集することが可能です。聴取する必要のある情報が出てきた場合も、患者さんの意識があればその場で聞けますし、追加の情報として身体所見を取ることもできます。情報量が全く違う、それが一つです。
もう一つの側面は、研修医の教育です。身体所見のとりかたやモニターグラフィックの見かた、レジデントやフェローが言ったことと指導医である集中治療医が言ったことのギャップなどがそのまま教育になります。当院に学びに来ている研修医は、それを求めて来ているようなところもあると思います。
ベッドサイド回診ではどのような点を重視しておられますか?
則末先生:
回診では見落としをなくすため、プレゼンテーションのフォーマット(表1)を用いて、神経系、循環器系、呼吸器系、消化器系、腎・電解質といったシステムベース(臓器ごと)でアセスメントをおこなっています。これは、特に重症患者さんでは重要です。ただし、システムベースであることの落とし穴として、各臓器の現状報告になってしまうことに留意が必要です。例えば、血圧が低いため昇圧薬を使っているという場合、その現状報告で終ってしまいがちですが、背景にある鑑別診断を挙げ、その問題を引き起こしている原疾患について話し合うことが重要です。システムごとにプロブレムを挙げる、例えば循環器系で低血圧というプロブレムを挙げ、それに対して必ず鑑別疾患を挙げるのです。そして、敗血症、肺塞栓症と挙げていくと、その診断のための検査や治療法のディスカッションにつながります。そうした点は非常に重視しています。
もう1点重視しているのは、患者さんにこの先どういう生活が待っているかを考えることです。例えば人工呼吸器が離脱できない場合、気管切開して施設に行くのか、あるいは人工呼吸器依存で生きていたくないという人であれば、抜管して緩和治療に移行するなど、その患者さんの主治医としてどうするかというところまで考えて治療の選択をすることです。
 平岡栄治・則末泰博・藤谷茂樹. 重症患者管理マニュアル. 2018,メディカルサイエンスインターナショナル, 東京.
平岡栄治・則末泰博・藤谷茂樹. 重症患者管理マニュアル. 2018,メディカルサイエンスインターナショナル, 東京.
RRS、CCOTの取り組みとACP
病棟における、患者さんの生命を脅かす疾患の早期発見、早期介入のために、どのような体制を構築しておられますか。
則末先生:
当院は、開設翌年の2013年にRRS(Rapid Response System)を、2017年にCCOT(Critical Care Outreach Team)を導入しました。RRSは、病棟のナースが患者さんに対して懸念があるときや、バイタルサインなどのRRS起動基準を満たしたときにナースによって起動され、集中治療医で構成するMET(Medical Emergency Team)が対応します。一方、CCOTはICUのナースによって構成されており、自ら病棟のハイリスク患者さんのところに赴き、必要に応じてRRSの起動を病棟のナースに促したり、直接METに連絡するなどします。CCOTのラウンドは、週2回で、ICU退出患者さんのなかでもハイリスク例を中心にしていることが多いです。チームは複数で構成していますが、1回のラウンドは1人の看護師がおこないます。
重症化の早期発見に関しては、RRSとCCOTの存在、そして看護師の教育が重要です。例えば院内で敗血症を発症した場合、最初に出てくる兆候として呼吸の異変が多く、RRS起動基準の中でも、特に呼吸数や呼吸様式は重要だと考えています。ですが、バイタルサイン(血圧、呼吸数、体温、脈拍)を定期的に検査するよう指示が出ていたとしても、呼吸数だけ測定していない施設が多いようです。呼吸数で気づけることは多いので、呼吸数を含めたバイタルサインを基本どおり測定すること、これがRRS起動を適切にできるようになるための、看護師教育の第一歩だと思っています。また、RRSは急変対応システムではなく、「急変させないシステム」であることを認識してもらうことがとても重要だと考えています。RRSの意味を正しく伝える和訳は「迅速対応システム」であり、急変対応システムという間違った言葉が一刻も早く使用されなくなることを願っています。
当院において、CCOT導入後の1年間(2017年7月~2018年5月)のCCOT総ラウンド件数は1,168件、RRS件数(1,000退院あたり)は、非CCOT導入期間10.0%(97件)からCCOT導入期間16.6%(150件)へと有意な増加が示されました(p=0.02、Fisher検定)。その結果、CCOT導入前後における、予期せぬ心停止数、死亡数は、ともに有意に減少しました(表2)。
 東京ベイ・浦安市川医療センター 則末泰博先生ご提供
東京ベイ・浦安市川医療センター 則末泰博先生ご提供
治療方針の決定にあたり、特に重視しておられるポイントについてお聞かせください。
則末先生:
人はそれぞれ異なった価値観をもっています。特に自分の死期が迫った時に、「どういう治療を受けたいか」、「どれぐらい侵襲的な治療まで頑張る事ができるか」、「どういう状況なら生きていくことを許容できるか」という点においても個人差があります。よって、患者さんの治療ゴールを決めるためにはACP(Advanced Care Planning)が必要です。
当院ではGIM入院時に、ほぼ全ての患者さんに治療ゴールを聞くようにしています。ICUでも、全例ではありませんが可能であれば聞いて、本人の意識がない場合はご家族に伺います。
治療ゴールを聞く際は、2つのことを知る必要があります。すなわち、最善のシナリオ(Hope for the best)と、求めていた転帰が得られない場合(Prepare for the worst)、つまり治療の撤退ラインをどこに置くかという点です。これは、完全緩和に移行するラインでもあります。
特に重視しているのは、ハイリスクの手術を受ける患者さんの術前ACPです。例えば手術の合併症で、残念ながら人工呼吸器依存になってしまった、あるいは人工呼吸器依存だけでなく人工透析と昇圧薬も続けないと生命が維持できず、敗血症を繰り返しているといった状況になった時、それでも1分1秒でも生きていることに意味があるという患者さんもいれば、その時点で緩和ケアを望む患者さんもいます。こうした点について本人の意思を聞いておけば、それに従うことができるので、ご家族の決断の負担は少なくて済むわけです。
ACPは、医療従事者や場合によっては非医療従事者など、誰がしてもいいのですが、医師が聞いた方がいい項目もあります。例えば、一般論として「どういう状態になったら生きていきたくないですか?」といったことは医師以外が尋ねて問題ありませんが、治療法の選択に関する項目の場合、選択肢となる治療法が患者さんにとってどのくらいの負担と効果があるかという点は医師でなければわかりませんから、医師が話し合う必要があります。
ACPはRRSやCCOTの取り組みに何らかの影響をもたらしているのでしょうか?
則末先生:
先にお示ししたように、CCOT導入後、異変に早く気づけるようになったことでRRS起動数は増え、さらに予定外ICU入室患者数は減少しました(表2)。その理由の一つとして、状態が悪化しつつある患者さんには、ICU入室だけではない、もう一つの選択肢がより適切である場合があり、RRSやCCOTによって急変前にその選択肢を患者さんやご家族と話し合うことが可能になるからです。ICUではないもう一つの選択肢とは、緩和治療のことであり、急変前に緊急にACPをおこなったり、もともとおこなわれていたACPに基づいて、ICUではなく、患者さんの希望する適切な緩和治療が提供されるわけです。
1分1秒でも心臓を動かすという目的だけで病院が動くと、個々の患者さんが望む死の質を無視したものになる可能性があります。本来であればご家族に囲まれて、手を握られ身体をさすられながらお亡くなりになれた人が、ICUに運ばれて挿管されてということになりかねません。医学的に適切な救命と、ACPを踏まえた緩和治療をしっかりするという、この両方の意識をRRSとCCOTがもっていることは重要だと思います。
治療に対する患者さんの意思を受け止める上で、特に留意されていることはありますか。
則末先生: 看護師は特に、患者さんやご家族の思いにとても敏感だと思います。例えば重症の敗血症患者さんの治療が長引くような状況において、「多分、患者さんは今みたいな治療が続くことを望んでいないと思いますよ」といったことを言ってきてくれるのは、看護師であることが多いです。看護師は医師以上にベッドサイドにいますし、ご家族とのコミュニケーションをとる機会も多いので、当院では、看護師の懸念を重視しています。
RRSやCCOTの今後のステップについてどのようにお考えですか?
則末先生: 看護師は入れ替わりの激しい職種ですので、一度できた文化が一瞬で廃れるという面もあります。ですので、次のステップというよりも、これまでに培ったシステムを如何に維持するかが重要だと思っています。一時期、呼吸回数の測定はほぼ全ての病棟で100%だったのですが、現在は90%前後と少し落ちてきていますので、定期的なレクチャーやキャンペーンが必要です。そもそも十人に一人でも呼吸数を測定しなくても良いと考えているナースがいること自体がとても恐ろしいことなのですが。今は、如何に継続するかというフェーズだと考えています。
RRSやCCOTの構築に向けてこれから取り組まれる施設にアドバイスをお願いします。
則末先生:
まず、施設全体としての取り組みが必要であり、そのためには、病院トップの理解を得ることが大切です。RRSが急性期充実体制加算の要件とされていますので、行政がバックアップしてくれているものは見逃さないようにして、しっかりと示していくこと。加えて、患者さん中心の医療をおこなう事に対するコンセンサスを得るというところだと思います。
当院においても、看護師が懸念を持てば、主科にも連絡しつつRRSも起動するという、このシステムを定着させるのは大変でした。「主科である自分たちがいるのに何でMETを呼んだんだ!!」とナースに対して怒る医師もいました。このようなシステムに対して医師の理解が得られにくいということは、どの施設でも起こりがちだと思います。当院では、「主科とMETの両方をコールすることはルールなので理解してください」と、張り紙をするなどもして、理解を求めるようにしました。
当院は2012年に新しい病院として出発しました。その際、日本にいながらにして世界標準の医療と世界標準の教育ができる施設にしようということで、キーメンバーとして、米国から帰国した医師が招聘されました。ですからRRSやCCOT、ACPは、立ち上げた医師にとっては何ら新しいことではなく、当然必要と考えられるものを取り入れて出発できたという背景があります。
患者さんを同じ医師が診る継続性という点では、主治医性には利点があるかもしれません。しかし、システムの継続可能性という意味では、やはり病院が公認したチームが主治医と一緒になって患者さんの安全を守る方がベターであることは間違いないと思います。
ICUやRRS/CCOTでご活躍の看護師さんにもお話を伺いました。
高島 幸 さん
東京ベイ・浦安市川医療センター 看護部
今までのご経験と現在のICUの違いについてお聞かせください。
高島さん: これまで、いくつかの急性期病院で一般病棟やCCU(Coronary Care Unit:冠疾患集中治療室)、ICUで勤務してきましたが、いずれの病院もopen ICUであったため、closed ICUでの勤務は当院が初めてでした。そのため、他のclosed ICUとの比較はできませんが、open ICUとの大きな違いは、「常に医師がいてくれる」という点です。open ICUでは、担当医が専門科の診療をしつつICUの患者さんを診ているため、ICUに常にいられるわけではありませんが、当院のICUでは集中治療専門医が常にICUにいてくれます。そのため、患者さんを看ている中で生じた疑問や懸念をすぐに相談したり、その場で患者さんを一緒にケアすることもできるため、とても安心して業務に従事できますし、治療介入も早いと感じています。当院ICU医師は、集中治療のスペシャリストということもあり、指示が細かく処置が多いので、当初は戸惑うことが多かったですが、丁寧に患者さんを看ることができていると実感しています。
RRS/CCOTにおける看護師の役割についてお聞かせください。
高島さん:
RRSには4つの要素が必要とされていますが(図1)、このうち、患者さんの異変や違和感を見逃さずRRSを起動する「起動要素」の役割を担っているのが一般病棟の看護師です。起動の際、「○○がおかしい」と明瞭に伝えることは容易ではなく、うまく伝えられないから起動しづらいと感じられるかもしれませんが、“なにかおかしい” や、起動基準を伝えるだけでも十分なのです。とにかく、気付いた異変や違和感を言葉にしてもらうことが、患者さんのそばにいる看護師の大事な役割だと考えています。
当院では、RRS委員会での決定事項や周知したい情報などは、リンクナースを通じて各病棟に伝達されるようになっており、「異変や違和感を言語化する重要性」についても院内で周知されるようにしています。
 日本院内救急検討委員会ホームページ:https://www.ihecj.jp/より引用
日本院内救急検討委員会ホームページ:https://www.ihecj.jp/より引用
CCOTには、いくつかの役割があると考えています。まず、予期せぬ心停止の回避を目的とし、ICU退室後やRRS起動後などのハイリスク患者さんを中心に、能動的に病棟へ赴き、必要に応じてRRSを起動する・病棟の看護師に対し起動を促す、という役割があります。
また、METは集中治療医で構成されていますが、CCOTは看護師で構成されているため、一般病棟の看護師はMETよりもCCOTに相談しやすいようです。このような相談窓口、という側面も役割の一つだと思います。
さらに、CCOTは、普段から人工呼吸器やドレーンなどの取り扱いに慣れているICUの看護師で構成されているため、ハイリスク患者さんに加えて、一般病棟で使用頻度の低い機器を使用している患者さんのところにも赴き、critical careの知識やスキルを指導する役割も担っています。
そして最後に、各病棟へのラウンドにより、終末期の患者さんに関わることも多いです。終末期かつ急変の可能性があると考えられる患者さんについて、急変時の対応方針が不明確であり、本来患者さん自身が望まない最期になりかねないと予想される場合、主治医に対してACPを行うことを提案する、という役割があります。とても難しいことではありますが、患者さんの人生観や価値観、そこから考えられる治療やケアを具体化することは、患者さんの人生の質を良くすることにつながるため、大切な役割だと考えています。
RRS/CCOTでの活動でやりがいに感じることや苦労されていることはありますか?
高島さん:
RRS/CCOTの活動を通して、患者さんの急変を未然に防ぐための知識やスキルを院内外に広めることができることをやりがいに感じています。
また、ICUでの患者さんは、様々な機器が装着されていたり、安静を強いられていることが多いため、ICU退室患者さんが日常に近い生活を送れるようになった姿を見られることが嬉しいです。また、そのような患者さん方を急変させることなく、スムーズに退院できるように働きかけられていることにやりがいを感じています。
一方、苦労していることは、院内研修です。則末先生も触れていますが、医師も看護師も異動が多いため、研修を運営するメンバーやリンクナースも毎年入れ替わってしまい、これまで培ってきたものを新しいメンバーに伝えることにとても苦労しています。毎年メンバーが入れ替わるということは、RRSの知識やスキルが広がっているという見方はできますが、研修を運営する側の苦労が絶えないのも正直なところです。
また、RRSが起動された症例の分析やフィードバックに十分な時間を割けられていないことに課題を感じています。予期せぬ心停止を増やさないためにも、病棟へのフィードバックが必要だと思うので、今後取り組みたいと考えています。
RRSの起動に迷うことはありますか?
高島さん: 当院のRRS起動基準(図2)の中に「患者に対する懸念」という項目がありますが、最近、当院の看護師を対象に実施した「RRS起動時の障壁に関するアンケート調査」では、 “なにかおかしい”と感じても、これを明瞭に表現することが難しく起動を躊躇してしまったり、起動基準には合致しているものの、起動せずに様子を見た、あるいは主治医に相談して様子を見ることにした、ということもあるようです。
 東京ベイ・浦安市川医療センター 則末泰博先生ご提供
東京ベイ・浦安市川医療センター 則末泰博先生ご提供
私自身、CCOTのラウンド時に迷う場面はとても多いです。ただ、心の中で生じた疑問は全て言語化し、どのような状態になったらICUやHCUに移動するか、というラインを設定し、病棟看護師に明確に伝達できるようにICU医師に相談しています。そうすることで、病棟看護師はRRSを起動しやすくなりますし、どこを観察しておけば良いかが明確であるため、患者さんの異変に早期に気付くことが可能となります。また、ICU医師(MET)に相談することで、実は情報共有にもなっており、いざその患者さんが急変してしまった/しそうになった場合でも、介入がスムーズにおこなわれるという側面もあります。
RRS/CCOTをうまく運用するにはどのような取り組みが必要だとお考えですか?
高島さん:
個別の症例についてきちんと振り返ることが重要だと考えています。その症例からの学びやその病棟特有の課題が見つかるため、次に何に取り組む必要があるかが見えてきます。また、シミュレーションも大事だと思います。コロナ禍の影響により、大勢で集まることは難しいかもしれませんが、オンラインを活用するなどして、RRS起動時の流れや急変に備えた練習をしておくと良いと思います。そして、則末先生も話されていますが、呼吸数測定の重要性を伝え続けていくことが大事だと考えています。
さらに、RRS/CCOTの取り組みでは、数多くのスタッフと接する機会があるため、良好なコミュニケーションのための関係構築や相談しやすい雰囲気づくりを意識しています。私自身、悩んだ時に相談しやすいスタッフが各病棟にいると安心ですし、リンクナースや病棟スタッフにとっても相談しやすい・発言しやすい雰囲気がなければ大切な情報が入ってこなくなってしまうため、特にコミュニケーションを大切にしています。これは、システムをうまく運用するためにも大事なことだと思います。
最後に
高島さん: RRS/CCOTは、患者さんが急変する前に介入する取り組みであることから、予後や退院後の生活の質の向上につながり、さらには患者さん・ご家族の人生の質の向上にもつながると思います。より多くの施設で導入されるように、本記事をご覧いただいた方と一緒になってRRS/CCOTを広められたら嬉しく思います。