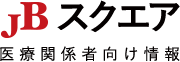ギラン・バレー症候群の歴史と概要
近畿大学医学部 神経内科 主任教授
楠 進 先生
(審J2006212)
―はじめに、近畿大学神経内科の概要についてお聞かせください。
楠先生:
近畿大学医学部は南大阪で唯一の医学部です。近畿大学神経内科は数少ない神経内科の中核施設なので様々な神経疾患の患者さんが来院されます。
神経内科が関わる主な四大疾患としては、脳血管障害、てんかん、認知症、頭痛がありますが、これらは脳神経外科や内科などの他科でも診られる疾患です。一方、神経内科が主に診る疾患として多いのはパーキンソン病です。近畿大学神経内科の特徴としては、免疫性神経疾患が多いことが挙げられます。例えば、多発性硬化症、視神経脊髄炎、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy:CIDP)、ギラン・バレー症候群(Guillain-Barré syndrome:GBS)、重症筋無力症などがあります。一つ一つは希少疾患ではありますが、カバーする疾患の数が多い点が神経内科の特徴です。
当教室では、GBS、CIDPや多発性硬化症をはじめとする免疫性神経疾患、末梢神経障害、パーキンソン病や運動ニューロン疾患などの神経変性疾患などに対する研究を行っています。研究テーマについては本人の希望を尊重し、他施設との共同研究を視野に入れて研究していく方針です。
私が主たる研究対象として扱っているのはガングリオシドなどの糖脂質、糖タンパク、プロテオグリカンなどのいわゆる「複合糖質」です。神経疾患は、様々な病態があり障害される部位が多様ですので、難しいと思われる医学生も多いのですが、分子種ごとに局在の異なるガングリオシドなどの複合糖質が、各症例の症状の多様性を解く鍵になるのではないかと考えています。
また当科では、GBSの診断に大変有用な「抗ガングリオシド抗体」を測定しています。ここ数年は、抗体測定依頼件数が増加傾向にあり、状況によりますが2~3週間程度で検査結果をお戻ししています。
近畿大学 内科学講座 神経内科部門(抗糖脂質抗体測定)
http://www.med.kindai.ac.jp/neuro/koutousisitu/koutousisitu.html
GBSについて
―GBSがどのような疾患であるかお聞かせいただけますか。
楠先生:
GBSとは、急性の多発性末梢神経障害をきたす自己免疫疾患です。多くは呼吸器感染や消化器感染などの先行感染後1~2週間程度を経て運動麻痺や感覚障害を発症します。その後、2~4週間以内に症候はピークに達した後軽快に向かいます。単相性の疾患ですが、稀に再発例の報告もあります1)。GBSの約60%に抗ガングリオシド抗体の上昇がみられます。ある種の先行感染の病原体にガングリオシド様構造を持つ糖鎖が含まれているため2)、その糖鎖部分を認識する抗体が産生されるとガングリオシドにも反応することになります。この抗ガングリオシド抗体が、末梢神経やシュワン細胞などを攻撃することで、末梢神経障害が生じると考えられています(図)3)。
神経を障害する病態は2週間から長くて1ヵ月程度続き、その後症状は回復に向かいます。治療を行うことで、多くの例では社会復帰が可能となりますが、約20%に後遺症が残る例があります。また、呼吸筋麻痺をきたして人工呼吸器の装着が必要になる例、自律神経障害によって血圧コントロールが不安定になる例、不整脈を発症する例などもあります。最悪の場合、死に至る例も稀にあります。
重症化する時は急速に悪化していきますので、比較的早い段階で重症か否かの判断ができます。重症化しても完治すれば通常の生活を送れますが、歩行障害が残り、車椅子で過ごさなければいけない状態になる例もあります。予後予測は必ずしも容易ではありませんが、一般的には急性期に重症化すれば後遺症も残る可能性が高いと考えられています。
■GBSの発症機序

―GBSは原著報告から100年が経過しました。その歴史を振り返りながら、病態と病型についてお聞かせいただけますか。
楠先生:
実はGBSの最初の報告は、1859年のLandryによる記述と考えられています4)。急性麻痺を発症後、比較的予後は良好という疾患について記載されていましたが、疾患概念として明確ではありませんでした。その後1916年にGuillainとBarré、Strohlにより腱反射消失や脳脊髄液の蛋白細胞乖離の所見(蛋白レベルは上昇するが細胞数は上昇しない)が報告され5)、それが原著となり「ギラン・バレー症候群」と呼ばれるようになりました。
1969年にAsburyらによる剖検所見の解析が行なわれ、リンパ球浸潤と脱髄がGBSの主要な病態であると報告されました6)。GBSの動物モデルとされた実験的自己免疫性神経炎(experimental autoimmune neuritis:EAN)においても、リンパ球や抗体がミエリンを攻撃することからGBSは一般的に脱髄疾患とされ、軸索障害については激しい脱髄が起こることで生じる、あくまで二次的な障害だと認識されていました。
しかし、1986年にFeasbyが軸索をプライマリーに障害するタイプが存在することを報告しました7)。当初この概念はなかなか受け入れられませんでしたが、1990年代には中国の農村部で軸索障害を起こす末梢神経障害が流行し8)、米国の研究者が詳しく解析したことをきっかけにGBSの軸索型が認識され始めました。その後の研究でアジアにおいては軸索型が占める割合が欧米と比べて高いことが報告されています9)-12)。軸索型では細胞表面のガングリオシドに対する抗体が高頻度に出現することも分かり、非常にユニークな特徴を持つ亜型であるとされました。
また、1956年にMiller Fisherにより、GBSと同様に先行感染の後、急性単相性の経過の眼球運動麻痺、運動失調、および腱反射消失を三徴とする疾患が報告され13)、フィッシャー症候群(Fisher syndrome:FS)と言われるようになりました。FSは前述の臨床経過や症状に加えて脳脊髄液の蛋白細胞乖離もみられることから、GBSの亜型と考えられてきました。1992年に我々のグループが特異的かつ高頻度な抗GQ1b抗体の存在を報告し14)、GBSと同様の病態機序による疾患であることが確認されました。
―病型の頻度と地域差には何が関連しているのでしょうか。
楠先生:
軸索型の先行感染としてCampylobacter jejuniが多いので、地域における衛生状態や環境面が軸索型の頻度に関係している可能性も考えられます。しかし、欧米と日本では衛生状態はさほど変わりませんが、軸索型の頻度は欧米に比べて日本で多いことが報告されており12)15)16)環境要因だけではないと考えられます。
人種により糖鎖に対する抗体の産生度合が異なる可能性も考えられます。例えば、糖鎖に対する抗体産生抑制因子があると仮定した時に、欧米人は多く、日本人では少ないといったような可能性です。さらに、人種により神経系に存在するガングリオシドの分布や濃度が異なる可能性もあります。これらは仮定であり、確認されたことではありませんので、今後の詳細な研究が必要と考えられます。