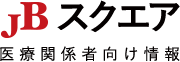ケースから考えるCIDPの治療

千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 准教授
三澤 園子 先生
(審J2409154)
※本⽂内に記載の薬剤をご使⽤の際には、各製品の電子化された添付⽂書をご参照ください。
― はじめに千葉大学病院脳神経内科についてお聞かせください。
三澤先生:
当科では、神経免疫疾患、神経変性疾患を中心とした入院診療や、末梢神経疾患をはじめとした神経内科領域の様々な疾患の外来診療を行っており、2020年度の入院総数は421名、外来診療の新患総数は1,412名でした。各神経疾患の専門医が高度医療を提供できる体制が整っていますので、POEMS症候群の患者さんが全国から集まるなど、他院での診断や治療が困難な患者さんも積極的に受け入れ、セカンド・オピニオンの依頼も多くいただいています。
『EAN/PNS* guideline』2021年版1)について
*European Academy of Neurology/Peripheral Nerve Society
― 2021年7月、『EAN/PNS guideline』の改訂版がオンラインで公表されました。2010年版2)からの主な改訂内容を教えてください。
三澤先生:
今回公表された『EAN/PNS guideline』では、2010年版からの変更点が多数あります。まず診断に関する主な変更点として押さえるべきは、臨床病型、診断カテゴリー、診断プロセスの3つです。
臨床病型に関しては、2010年版ではTypical CIDPとAtypical CIDPの2つに大別され、Atypical CIDPの中にいくつかの臨床病型が含まれていました。2021年版では、Typical CIDPの表現はそのままですが、Atypical CIDPはCIDP variantsに変更になりました(図1)。将来的にはCIDP variantsという病型は、CIDPとは異なる疾患として分類されていくのではないかと考えられます。
図1 主な臨床病型

CIDP variantsに含まれる病型にも名称変更があります。局所型CIDP(Focal CIDP)はそのままですが、多巣性脱髄性感覚運動型CIDP(MADSAM)はMultifocal CIDP、遠位優位型CIDP(DADS)はDistal CIDP、純粋感覚型CIDP(Pure sensory CIDP)はSensory CIDP、純粋運動型CIDP(Pure motor CIDP)はMotor CIDPと名称が変わりました(表1)。
表1 CIDPの臨床病型分類

Van den Bergh PYK, et al. J Peripher Nerv Syst 2021;1-27. を基に作表
診断カテゴリーは、2010年版ではDefinite、Probable、Possibleの3つに分類されていましたが、2021年版はCIDPとPossible CIDPの2分類となっています。
また、診断の手順が明確に示されました。診断はClinical criteria(臨床基準)→Electrodiagnostic criteria(電気診断基準)→Supportive criteria(補助基準)(図2)の3つのステップで進められます。更に、注意すべき特徴がRED flagsとして示されており、RED flagsの該当がなければElectrodiagnostic criteriaに進みます。RED flagsは臨床病型毎に提案されており、それぞれ鑑別すべき疾患が念頭に置かれています。
今回の改訂では、Electrodiagnostic criteriaに感覚神経の神経伝導検査所見が加わりました。運動神経で2神経以上の脱随所見が、感覚神経で2神経以上の異常所見があれば、臨床病型も踏まえてCIDPと診断されます。しかし、Electrodiagnostic criteria を満たさなければPossible CIDPとなり、Supportive criteriaの判定に進みます。Supportive criteriaには治療反応性の有無、画像検査(超音波、MRI)、髄液検査が含まれます。これらの中から2つ以上の項目を満たす場合に、CIDPと診断されます。
図2 CIDPの診断プロセス

― CIDPとの鑑別を考慮すべき疾患や鑑別のポイントを教えてください。
三澤先生:
初期診断としては、まず臨床症状からCIDPと他疾患の鑑別を行います。Typical CIDPは診断に迷うことは少ないと思いますが、非対称性もしくは多発性単神経障害の臨床症状を呈するMultifocal CIDP、対称性で遠位優位のDistal CIDPは他疾患との鑑別が難しいケースがあります(図3)。CIDPと診断をされたけれども、最終的には半数近い症例が別の疾患であったという報告もあり3)、CIDPと他疾患を的確に鑑別していくために、RED flagsが示されているわけです。
Multifocal CIDPに関しては、多巣性運動ニューロパチー(MMN)、遺伝性圧脆弱性ニューロパチー(HNPP)、血管炎性ニューロパチー(VN)などとの鑑別を意図して、感覚異常なし、家族歴、抗核抗体(ANA)や抗好中球細胞質抗体(ANCA)などがRed flagsとして挙げられています。
Distal CIDPに関しては、シャルコー・マリー・トゥース病(CMT)、遺伝性ATTRアミロイドーシス、ALアミロイドーシス、POEMS症候群、糖尿病ニューロパチーなどの鑑別を意図して、家族歴、血糖値、単クローン性γグロブリン(Ig)血症などが、Red flagsとして挙げられています。これらのRed flagsは、診断を再考する際にも有用です。
図3 初期診断においてCIDPと識別すべき疾患

Allen & Lewis, Neurology 2015;85:498-504; Kaplan et al., Muscle Nerve 2017;55:476-482を基に作図
CIDPは診断が難しい疾患です3)。本ガイドラインに沿って、CIDPと他疾患との鑑別を実臨床でどのように行っていくかについて自験例を提示します。
※ご紹介する症例は臨床症例の一部であり、全ての症例が同様の経緯を示すわけではありません。
症状:X年1月 駆け足ができない、 両足のしびれ(下肢遠位筋の運動・感覚障害)
2月 階段が昇れない、段差でつまずく(下肢近位筋・遠位筋の筋力低下)
3月 ペットボトルが開けられない、電話帳が持ち上がらない(上肢近位筋の筋力低下)
神経学的所見:筋萎縮なし
三角筋(4、4)、握力(5、4kg)、
腸腰筋(4、4)、前脛骨筋(4、4)の筋力低下
四肢腱反射の消失
症例報告者:三澤園子先生
進行性または再発寛解の臨床経過が8週以上、対称性の四肢の症状、遠位および近位筋の筋力低下、2肢以上の感覚障害があり、四肢の腱反射が低下ないし消失というTypical CIDPのcriteriaを満たし、Red flagsはないことから、神経伝導検査を行いました。
神経伝導検査では、正中神経で遠位潜時の延長および運動神経伝導速度(MCV)低下が認められました。運動神経の2神経以上に脱髄所見が、感覚神経の2神経以上に異常所見が認められたことから、この症例はCIDPと診断できます。もし神経伝導検査の基準を満たさなかった場合は、Supportive criteriaに進み、治療反応性があるか、MRIで神経肥厚が確認されるか、などの所見で補完することになります。
※ご紹介する症例は臨床症例の一部であり、全ての症例が同様の経緯を示すわけではありません。
現病歴:X年1月 両足のしびれ(遠位筋の感覚障害)
9月 両足先の筋力低下
前医:脱髄・髄液蛋白上昇
→診断:CIDP
→ステロイド・IVIg(静注免疫グロブリン):筋力低下の自覚的改善
12月 筋力低下が再増悪
X+1年 ステロイド・IVIg治療継続
12月 両足浮腫、胸腹水貯留
症例報告者:三澤園子先生
Distal CIDPの臨床症状は、遠位優位の筋力および感覚の低下で、他はTypical CIDPのClinical criteriaに準じることとされています。この基準に沿って本症例を評価すると、Distal CIDPの可能性が示唆され、治療が開始されました。しかし、免疫治療に対する反応性が乏しく、浮腫や胸腹水等の随伴症状を合併してきたため、当院へ紹介されました。精査により、M蛋白陽性、VEGF高値から、POEMS症候群と診断しました。
今回のガイドラインでは、ステロイド、IVIg、血漿浄化療法の各治療に不応の場合は、都度診断を再考するか、専門施設に紹介を考慮することと明記されています。CIDPの診断が時に難しいことが、専門家の間でもコンセンサスである証左と考えられます。
― 抗体検査の有効性について教えてください。
三澤先生:
Distal CIDPと鑑別すべき疾患は多く、抗ミエリン随伴性糖蛋白 (MAG)抗体陽性のニューロパチー、抗neurofascin 155(NF155)抗体、抗コンタクチン1(CNTN1)抗体など傍絞輪部の分子への自己抗体陽性のニューロパチー、アミロイドーシス、POEMS症候群などが挙げられます。
ガイドラインでは、CIDPが疑われる全症例において、M蛋白の検査が推奨されています。ALアミロイドーシスやPOEMS症候群ではM蛋白が微量である場合があり、電気泳動では検出できず、免疫固定で初めて検出できることがあり注意が必要です。IgMクラスの M蛋白が陽性の場合には、抗MAG抗体の評価が推奨されます。
また、NF155、CNTN1、コンタクチン関連蛋白1(Caspr1)などに対する自己抗体陽性の一群は、これまではCIDPに含まれていましたが、今回のガイドラインではAuto-immune nodopathies(自己免疫性結節性疾患)として区別されました。
IVIgへの抵抗例で、NF155抗体やCNTN1抗体陽性例の特徴が当てはまる例では、抗体検査を積極的に検討していただきたいと思います。
CIDPの治療について
― CIDPの初期治療と維持治療について教えてください。
三澤先生:
今回のガイドラインでは、初期治療、維持治療という言葉が明確に示されました。CIDPの初期治療として推奨されるのはIVIgおよびステロイドで、次に血漿浄化法です。維持治療として推奨されるのは、ステロイド、IVIgまたは皮下注Ig(SCIg)、血漿浄化法です。
ステロイド投与法としては、Daily regimen、Pulsed regimenがありますが、至適な投与レジメンは明確ではありません。合併症や医師の経験、患者の希望などに応じて使い分けていくことになると思います。
IVIgに関しては、400mg/kg体重/日で5日間の導入療法後、1,000mg/kg体重/日を3週間隔、または週1回のSCIgによる維持治療になります。IVIg投与直後は、Igの血中濃度が急速に上昇した後、2~4日で低下し、約1ヶ月かけて半減します。血中濃度上昇時には、頭痛、血栓症などの有害事象が発現するリスクが高くなります。血中濃度の低下に関連して筋力低下が見られることがあります。Igは血中濃度が高くなるほど半減期が短くなる傾向があり、IVIgはSCIgよりもIgの血中濃度が上がるため半減期が短く、SCIgではIVIgほど血中濃度が上がらないため緩徐に下降するという特徴があります。維持治療としてのIVIgとSCIgに効果の差は示されていません4)。
IVIg療法の効果判定の実際についても言及されています。全ての症例が初回治療に速やかに反応する訳ではないため、導入療法後にそのまま3週ごとの維持治療(2-5回)へ移行する方法と、初回導入治療の数週後に同用量の投与を再度行って反応性を見る方法がガイドラインで紹介されています。IVIg、ステロイド、血漿浄化法による治療効果が不十分で、病勢コントロールが難しい場合、治療薬の併用や免疫抑制薬の投与を考慮するとしています。
免疫抑制薬の効果は、エビデンスレベルとしては低く、”Advise to use”という表現になっています。免疫抑制薬はIVIg、ステロイド、血漿浄化法による治療不応な場合や、Igやステロイド減量のための併用薬として用いられますが、Fingolimod、MTX、IFNβ1a※などは非推奨とされています。
※「記載の薬剤については、承認外の内容が含まれておりますので、最新の電子化された添付文書をご参照ください。」
― IVIg製剤はどのように使い分ければいいですか。
三澤先生:
IVIg製剤には幾つかの種類がありますが、使い分けの観点からの有効性や安全性のエビデンスはありませんので、様々な判断尺度、評価尺度から総合的に判断して選択することになります。適応疾患、用量、浸透圧、ナトリウムや糖の含有量などが製剤により異なるため、高齢者や、心疾患・腎疾患・糖尿病などの合併症を有する患者さんに投与する場合は注意が必要です。
5%製剤と10%製剤がありますので、病型、年齢、リスク、生活スタイル等を考慮して選択することが可能です。また、溶解が必要な製剤と不要な製剤がありますので、ご施設の状況により、調剤のしやすい薬剤の選択が必要になることもあります。
― 治療薬の減量や中止を判断する上でのポイントを教えてください。
三澤先生:
CIDPには単相性で比較的早期に病勢が低下する方と、再発・寛解を繰り返す方がいらっしゃいます。単相性の方は維持治療が本来必要ではないため、適切に免疫治療を漸減・中止する必要があります。一方、再発・寛解を繰り返す方は、維持治療をしっかり行い、十分に病勢をコントロールして、二次的な軸索変性を予防する必要があります。
IVIgによる維持治療中に、筋力が十分に維持できるようになれば、患者さんと相談をして減量を検討します。再発を懸念する方に対しては、コミュニケーションを充分に取りながら、拙速にならないように進めます。治療反応性が良い場合には、再発しても治療を再開すれば筋力が戻るといったこともお話しして、不安を取り除きながら進めていくことも重要です。
ガイドラインでは、臨床的に症状が安定していたら、最初の2~3年は半年から1年ごとに減量、投与間隔の延長、中止を考慮とされています。
― 治療反応性の評価はどのようにすればよいでしょうか。
三澤先生:
治療反応性の評価は、患者さん自身の感覚よりも、客観的指標で評価することが重要です。ガイドラインでは幾つかの指標が示されています。幾つか例を挙げると、Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment(INCAT)スコア1以上、Medical Research Council(MRC) sumスコア2~4以上、握力の10%以上の改善は、治療反応性ありとされています。
専門医へのメッセージ
― CIDPを診療される先生方へのメッセージをお願いします。
三澤先生:
今回のガイドラインのポイントの一つは、診断プロセスが臨床病型で明確に分けられ、それぞれの病型における鑑別診断の注意点が詳細に示されていることです。特に、標準治療への反応性が乏しい際に、都度、診断を見直すことが明記されていることは印象的でした。鑑別の対象となる疾患の治療はCIDPの治療とは異なります5)。革新的な治療が実用化されている疾患もあります。早期の診断と治療は予後に大きく影響するため、いずれの疾患も的確に診断をすることは医師の責務であると考えます。
現在、日本神経学会のガイドライン作成委員会では、日本のガイドライン*の改訂作業を進めています。改訂版は2022年度中に発行される見通しです。使いやすいものになるよう努めたいと思います。
*2024年5月に日本神経学会から「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy:CIDP)・多巣性運動ニューロパチー(multifocal motor neuropathy:MMN)診療ガイドライン2024」が発刊されています。