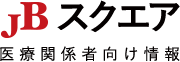肺移植の基礎と抗体関連型拒絶反応に対する治療の実際

監修 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師 中島大輔先生
▶プロフィールを見る
【指導医、専門医、認定医】
日本外科学会外科専門医、日本外科学会外科指導医、日本呼吸器外科学会呼吸器外科専門医、日本移植学会移植認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医
【評議員、学会委員会所属】
日本呼吸器外科学会評議員、日本呼吸器外科学会移植委員会委員、日本移植学会人材育成委員会委員、日本移植学会DCD donation推進ad hoc委員会委員、日本移植学会Machine Perfusion委員会委員
【他の所属学会】
日本胸部外科学会会員、日本肺癌学会会員、日本呼吸器学会会員、ISHLT会員、ESTS会員
※本⽂内に記載の薬剤をご使⽤の際には、電子添文をご参照ください。
▮ 日本における肺移植の現状
2010年7月に臓器移植法が改正され1)、家族の書面による同意のみで臓器提供が可能となって以降、脳死下臓器提供数の増加に伴い肺移植数は急増している2)。一方で、肺移植医療の認知度の上昇に伴い肺移植を希望する登録患者数も急増しているため、日本では今なおドナー不足が深刻な問題となっており、重症例に対して生体肺移植を要する状況が続いている。
肺移植は内科的治療を最大限に行っても病勢の進行を抑えることができず、肺移植以外に救命できる有効な治療手段がない慢性進行性肺疾患が適応となる。肺移植の適応の検討では、除外条件3)がより重要である。移植後は生涯免疫抑制療法が必要となるため、肺以外の臓器に活動性の感染巣が存在しないこと、肝臓や腎臓など他の重要臓器に進行した不可逆的障害が存在しないこと、悪性腫瘍がないこと、移植後の合併症や死亡リスクを高めるような極めて悪化した栄養状態や極端な肥満がないことが条件となり、さらに周術期のリハビリテーション能力を期待できない場合には、移植の適応外となる3)。
脳死両肺移植の適応疾患3)には、気管支拡張症やびまん性汎細気管支炎などの感染性肺疾患や重篤な肺高血圧症などが挙げられる。一方で、ドナー不足の日本では、間質性肺炎、肺気腫、リンパ脈管筋腫症などといった疾患は、原則、左右の肺を2人の患者さんで分け合う脳死片肺移植の適応となる。こうした各疾患の移植登録基準は国際心臓肺移植学会(ISHLT)のコンセンサスドキュメントに詳細に記載されている4)。
肺移植レシピエントの一般的適応指針および除外条件を表1に示す3)。
表1. 肺移植レシピエントの一般適応指針および除外条件

肺移植関連学会協議会: 肺移植レシピエントの適応基準.
https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/kanren/
(最終アクセス:2025年5月20日)
脳死肺移植を希望する患者さんは、まず日本に11ある肺移植施設のいずれかで適応評価の検査を受け、その結果に基づき、中央肺移植検討委員会で適応ありと判断されると日本臓器移植ネットワークに登録が可能となる。登録後は血液型や、肺の大きさが適合した患者さんに対し、登録順にドナー肺が斡旋される。2025年1月時点で肺移植希望の登録患者数は634名となっている5)。したがって、現在の日本における肺移植の平均待機期間は約930日6)であり、待機死亡率は約40%7)となっている。
生体肺移植は1993年に南カリフォルニア大学で開発された術式であり8)、1998年に日本に導入された。通常の生体肺移植では、健康ドナー2人から提供される右もしくは左下葉を、レシピエントの両肺として移植する。
図1は、日本の脳死肺移植数と生体肺移植数を年次毎に示したものである2)。日本の肺移植は1998年の岡山大学での生体肺移植の成功に始まり、2000年の東北大学と大阪大学で行われた脳死肺移植が続き、これまで着実な発展を遂げてきた9)。2010年に臓器移植法が改正され、脳死肺移植数は増加しているものの、重症例や小児に対し、生体肺移植を必要とする状況が続いている。実際に、生体肺移植は年間10~20例に行われており、日本の全肺移植数の23.7%を占める重要な治療法となっている2)。
図1. 日本における脳死肺移植数と生体肺移植数

肺および心肺移植研究会レジストリー: 2025年レジストリーレポ―ト.より一部改変
https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/registry/
(最終アクセス:2025年5月20日)
生体肺移植の利点として、移植肺の虚血時間が短いこと、脳死ドナー肺に認めるような外傷、感染、誤嚥といった障害がなく、理想的なグラフトであることが挙げられる。このため、生体肺移植後は、虚血再灌流障害による急性移植肺機能不全 (PGD)の発症頻度が、脳死肺移植と比較し少なくなっている10)。また生体肺移植における血縁者からの臓器提供は、拒絶を起こしにくいなど免疫学的に有利な可能性が期待される10)。一方で、生体肺移植では、健康なドナーからの肺の摘出を必要とする倫理的問題を抱えている。従って、生体肺移植は、病気の進行が速く、脳死ドナー肺の斡旋を待つことができない重症患者、すなわち生体肺移植でしか救命できない患者のみが対象となる。適応疾患としては、間質性肺炎と並んで、造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(GVHD)による肺障害が多いのが特徴である2)。
このように、生体肺移植は重症例に対して施行されているものの、5年および10年生存率はそれぞれ72.20%、59.44%と脳死肺移植後の成績と同様に良好であることが示されている(図2)2)。
図2. 術式別肺移植後生存率

肺および心肺移植研究会レジストリー: 2025年レジストリーレポ―ト.より一部改変
https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/registry/
(最終アクセス:2025年5月20日)
▮ 1秒量低下の早期発見の重要性
肺は細菌やウイルス、真菌などを含む環境と常時接するため感染を起こしやすい。また、これらに抵抗するために、もともと免疫機構が発達した臓器であり、拒絶反応も生じやすい。したがって、本邦における肺移植後の死因の約3割は感染症、約2割は拒絶による慢性移植肺機能不全(CLAD)、約1割が悪性腫瘍となっている2)。なかでも、CLADは拒絶により閉塞性細気管支炎(BOS)もしくは拘束性肺障害(RAS)によって1秒量が低下した病態であり、現時点で有効な治療法はない。
そのため、1秒量の低下を早期に発見し、治療介入することで、その進行をできるだけ早く抑えることが重要となる。退院後、患者さんがスパイロメトリーを用いて毎日1秒量を測定し、自己管理表へ記録することにより、早期発見に努めている。しかし、早期治療介入を行っても1秒量の低下が著しい場合には、再肺移植を考慮しないといけない症例もある。その場合には、再度適応評価を行い、日本臓器移植ネットワークに登録し、待機する必要があるので、いずれにしても早期発見が重要となってくる。
▮ 抗体関連型拒絶反応(AMR)の診断とdnDSAが予後に与える影響
CLADのリスク要因の1つである抗体関連型拒絶反応(AMR)において重要となる抗体は、ドナーのHLA抗原に対するドナー特異的抗体(DSA)である。現在、肺移植後AMRの診断は、ISHLTのコンセンサスレポートに基づいて行われており、グラフト機能不全の有無によってClinical AMR(機能不全あり)もしくはSubclinical AMR(機能不全なし)に分類される。このほか、病理所見で移植肺の組織障害やC4d沈着を認める場合や、血液検査でDSA陽性であればAMRと診断される(図3)11)。
図3. Clinical AMR と Subclinical AMR の診断

中島大輔先生ご提供 Levin DJ et al.: J Heart Lung Transplant. 35: 397-406, 2016. より作成
ただし肺移植では、AMRの病理組織所見は非特異的であること、またC4d沈着の頻度は稀であるため、診断のために生検を行う症例は多くなく、DSAの有無によって診断されることが多い。dnDSA発現と肺移植の予後との関連を検討したコホート研究12試験のメタアナリシスでは、dnDSA発現率は平均30.8%であり、その80.6%はDQローカスに対するDSAであること、また移植前にHLA抗体陽性の患者は、dnDSA発現リスクが高いことが報告されている12)。また、予後との関連では、dnDSAの発現はCLAD発症リスクや死亡率を高めることが示されている12)。
当院における脳死肺移植後と生体肺移植後のdnDSAを比較した結果では、脳死肺移植後のdnDSA発現率は19.3%、移植後から発現までの平均期間は196日であったのに対し、生体肺移植後ではそれぞれ、6.8%および1,256日という結果であった10)。さらに予後との関連では、脳死肺移植後のdnDSAは、全生存期間(OS)およびCLAD free-survivalを有意に低下させたのに対し(HR 3.46 , 95% CI 1.59-7.57, p=0.002およびHR 2.23 , 95% CI 1.08-4.63, p=0.003, log-rank検定)、生体肺移植後ではdnDSAと移植後の予後との関連は認められなかった(HR 1.25, 95% CI 0.09-17.29, p=0.87, log-rank検定)10)。
生体肺移植では、グラフトの虚血時間が短く、グラフトに障害がないことから移植後の虚血再灌流障害によるPGDが少なく、また血縁者からの臓器提供はHLAのミスマッチ数が少ないことなどにより、移植後早期の免疫反応増幅によるdnDSA発現を抑制できるのではないかと考えられる。
臓器移植抗体陽性診療ガイドライン202313)においても、dnDSAは一般的に肺移植後の予後の低下に影響し得ること、特にDQ抗体、DQ locusに対するdnDSAは肺移植後成績(CLAD発症や生存率)に影響を与え得るとされている。
▮ Clinical AMRへの治療介入
グラフト機能不全を伴うClinical AMRには治療介入が必須となる。ワシントン大学は、成人肺移植患者484例に対する501件の肺移植におけるAMRに対する治療成績をレトロスペクティブに解析し報告している。診断基準を全て満たしたDefinite clinical AMRの発症率は21例(4.2%)であった。血漿交換、免疫グロブリン(IVIg)、リツキシマブを併用した治療後にDSAが遷延した12例のうち、6例はAMRで死亡、残りの6例はCLADで死亡した14)。一方、DSAが消失した9例は、全例がCLADを発症したものの、観察期間内の死亡は3例のみであった。Clinical AMRの予後は悪いものの、治療介入により生存期間延長の可能性が示唆されている(図4)14)。
続いて、肺移植患者255例を対象にレトロスペクティブに解析した豪州アルフレッド病院の報告15)では、Possible clinical AMR を9例(3.5%)に認めた。ステロイドパルス、血漿交換、リツキシマブ、IVIgによる併用療法の結果、臨床所見の改善・退院を5例に認め、うち2例はCLADにより死亡した。改善を認めなかった4例では、全例がCLADにより死亡した。臨床所見の改善を認めた5例に共通していたのは、全てのDSAの平均蛍光強度(MFI)が低下したこと、および、MFIが5,000を超えているDSAのMFIが、5,000以下に低下したことが挙げられている(図5)。
日本の3施設において肺移植患者525例を対象に実施された、AMRに対するリツキシマブの使用実態調査16)では、Clinical AMR発症率は2.7%(小児1例、成人13例)であった。血漿交換、IVIg、リツキシマブ、抗胸腺細胞グロブリン(ATG)などによる併用療法を実施した結果、未回復・グラフト廃絶を認めた6例は最終的に全例グラフト廃絶に至り、一旦回復を認めた8例においても5例がグラフト廃絶に至った(図6)。このように、日本のデータにおいてもClinical AMRは非常に予後不良であることが示されているが、回復を認めた8例中3例ではグラフト生着を維持できており、治療介入によってグラフト生着期間の延長を期待できる可能性も示唆されている。
臓器移植抗体陽性診療ガイドライン202313)では、「急性のグラフト機能不全が確認されたPossible/Probable/Definite clinical AMRに対して治療介入を考慮しても良い〈推奨グレード 弱 エビデンスレベル C〉」とされており、治療法としては、「原因抗体の除去および新たな抗体産生の抑制を目的とした治療の実施を考慮しても良いが、確立した治療レジメンはない〈推奨グレード 弱 エビデンスレベル C〉」とされている。
図4. Definite clinical AMR に対する DSA 消失の有無別の治療成績

Wit CA et al.: J Heart Lung Transplant 32: 1034-40, 2013. より作図
【試験概要】成人肺移植患者484例に対する501件の肺移植後のAMRに対する治療成績をレトロスペクティブに解析
【Limitations】重症でないAMR症例が認識されなかった可能性や、除外された原因不明の同種移植片機能不全症例がAMRであった可能性がある。肺におけるC4d染色の解釈は困難であり、C4d沈着は定義の非実用的な要素である可能性がある。DSA陽性の定義にMFI閾値を用いたが、現在広く受け入れられているDSA陽性の定義はない。
図5. 試験概要

Otani S et al.: Transplant Immunology 31: 75-80, 2014. より作図
【試験概要】肺移植後のpossible clinical AMRに対する、ステロイドパルス、血漿交換、リツキシマブ、IVIgによる併用療法の治療成績をレトロスペクティブに解析
【Limitations】個々のHLA対立遺伝子に対する特異的抗体の傷害性の評価は、現状では限界がある。MFIは力価とは一致せず、血清阻害物質の存在がDSA分析を無効にする可能性がある。本研究は、これらに対処する上で十分な検出力を有していない。
図.6 肺移植AMRに対する治療成績

芳川豊史ら: 移植 56: 53-68, 2021. より作図
【試験概要】肺移植患者525例における肺移植後AMRに対する治療成績をレトロスペクティブに解析
【Limitations】本研究は少数例のレトロスペクティブ研究である。
▮ Subclinical AMRに対する先制治療
dnDSA陽性のSubclinical AMRに対し先制治療を実施したワシントン大学の報告17)では、dnDSA陽性症例(56.0%)に対しIVIg単独、または感染や白血球減少を認めない症例ではIVIgとリツキシマブを併用投与した結果、DSA消失率は62.3%であったことが示されている。
DSA陽性群における死亡は26.2%(17例/65例)、BOSによる死亡は10.8%(7例/65例)であった。DSA陰性群における死亡は17.6%(9例/51例)、BOSによる死亡は8.6%(6例/51例)であった。また、治療後にDSAが消失すれば、遷延群と比較し、BOS free-survival(p=0.03, Log rank検定)、OS(生存率)(p<0.01, Log rank検定)ともに有意に良好である結果が示されていた(図7)。
図7. 治療介入の有無別の BOS free-survival 及び生存率

Hachem RR et al.: J Heart Lung Transplant 29: 973-80, 2010.より一部改変
【試験概要】肺移植後のDSA発現例に先制治療を実施し、DSAの有無別に臨床転帰を比較
【Limitations】ランダム化比較試験ではなく、DSAを発現したが抗体指向性治療を受けなかった対照群が含まれていない。DSA陽性の標準的な定義はなく、本研究のDSA発現数は当センターが用いた陽性の定義に影響されている可能性がある。
もう1つの報告は、dnDSA陽性症例への治療介入に関するハノーバー大学からの報告18)である。AMR症例の大半がSubclinical AMRであり、先制治療が行われていた。先制治療のプロトコールは時期によって異なっていたものの、2017年4月より前にはIVIgとリツキシマブの併用療法が行われており、2017年4月以降はIVIg単独療法が行われていた。Clinical AMRに対しては血漿交換、IVIg、リツキシマブの併用療法が行われた。その結果、DSA陽性群および陰性群における4年グラフト生着率は、79%および81%(p=0.58, Log rank検定)、4年生存率は82%および83%(p=0.59, Log rank検定)、4年CLAD free-survivalは82%および78%であった(p=0.83, Log rank検定)(図8)。治療後のDSA消失率は91%であったが、Clinical AMRではDSA消失率が低く、グラフト生着率も不良であった。
図8. グラフト生着率、CLAD free-survival

Ius F et al.: Am J Transplant 18: 2295-304, 2018. より作図
【試験概要】肺移植後にDSAを発現し先制治療を受けたDSA陽性群とDSA陰性群の臨床転帰をレトロスペクティブに比較
【Limitations】無治療のeDSA+患者は少数であったため、eDSA+/無治療患者に代えてeDSA-患者を対照群とした。また、早期DSA患者のみを対象とした。
▮ 日本における肺移植後のAMRに対するIVIg使用実態¹⁹⁾
日本において2001年4月から2022年3月までに、肺移植後AMRに対しIVIg投与が確認された4施設48例(成人41例、小児7例)の調査結果を示す。AMR発症例のうち39例(81.3%)が急性で、発症時期は移植後から中央値0.5ヵ月であった。IVIgの単独投与が行われた症例(37.5%)はおそらくSubclinical AMRであり、IVIg、血漿交換、リツキシマブやステロイドパルスが併用されていた症例はClinical AMRであったと想定される(表2)。ほとんどの症例においてAMRの転帰はDSA抗体価や画像所見で評価されており、改善41例(85.4%)、維持4例(8.3%)、悪化2例(4.2%)であった。
IVIg投与前後のDSA抗体価の推移は、Class ⅠおよびClass Ⅱを共に含んだDSA低下率は92.6%、消失率は62.3%であった(図9)。
使用実態調査において、副作用は6/48例(12.5%)に7件認められた。小児7例には副作用を認めなかった。重篤な副作用を4例(9.8%)に5件認めた。腸壁気腫症が1例(2.4%)、サイトメガロウイルス感染が1例(2.4%)、網膜血管瘤が1例(2.4%)、出血性膀胱炎が1例(2.4%)、移植後リンパ増殖性疾患が1例(2.4%)であった。非重篤な副作用は2例(4.9%)2件で、サイトメガロウイルス感染が1例(2.4%)、肝機能異常が1例(2.4%)であった。いずれの事象も免疫グロブリン製剤との関連は不明であった。しかしながら、IVIg投与と有害事象の発現に直接的な関連は無いと考えられ、IVIg療法は比較的安全に施行できる可能性がある。
こうした結果から、肺移植後のIVIg併用療法は、循環DSAの低下・消失によりAMRを改善できる可能性が示唆されている。
表2. IVIg との併用療法の組み合わせ

中島大輔ら: 移植 58: 371-80, 2023.
[利益相反]一般社団法人日本血液製剤機構より中島先生に
論文執筆業務委託料をお支払いしている
図9. IVIg投与後のDSA抗体値の変化

中島大輔ら: 移植 58: 371-80, 2023.より作図
【試験概要】肺移植後AMRに対しIVIg投与が確認された患者におけるAMRの治療内容と経過を調査
【Limitations】少数例のレトロスペクティブ解析であり対照群との比較試験ではない。
臓器移植抗体陽性診療ガイドライン202313)では、「抗体陽性症例において、原因抗体の除去を目的とした治療の実施を考慮しても良いが、確立した治療レジメンはない〈推奨グレード 弱 エビデンスレベル C〉」とされているものの、IVIgは重要な治療選択肢の一つと考えられている。また、治療後もDSAが持続的に遷延する症例は、消失する症例より予後が悪い可能性があることが示されている14)。ただし一方で、治療をしなくてもDSAが消失する症例も認められるため14)、現時点ではSubclinical AMRに対する先制治療を支持するエビデンスは十分ではないことから、同ガイドラインでは推奨に関するステートメントは行われていない13)。
献血ヴェノグロブリンIH10%静注における「抗体関連型拒絶反応の治療」に関する電子添文
(2025年5月時点)」の記載事項 一部抜粋
4.効能又は効果
下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療
腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植
6.用法及び用量
通常、人免疫グロブリンGとして、1日あたり1回1,000mg(10mL)/kg体重を2回点滴静注する。ただし、患者の年齢及び状態に応じて適宜減量する。なお、必要に応じて追加投与する。
7.用法及び用量に関連する注意
7.9 本剤は投与開始から10日間以内を目安に2回の投与を完了するが、患者の年齢及び状態に応じて適宜調節すること。
▮ 今後の展望
肺移植後のAMRはCLAD発症リスクや死亡率を有意に高めることが示されていた。特にグラフト機能不全を伴うClinical AMRの予後は極めて不良であるが、治療介入により生存期間の延長も期待されている。したがって、血漿交換、リツキシマブ、IVIg、ATGなどを併用した治療が必須となるが、そのプロトコールは確立されていない。今後、多施設での無作為比較試験によるClinical AMRに対する併用療法のエビデンス構築に期待したい。
Subclinical AMRに対するIVIgを用いた先制治療においても有効性が示されている一方で、無治療でもDSAが消失する症例も存在するため、現時点ではSubclinical AMRに対する先制治療を支持するエビデンスが十分でない。今後、対照群(無治療)との比較において、先制治療が有効とされるSubclinical AMRの選定、さらにはそうした適応症例における先制治療の前向き試験により、プロトコールの確立にも期待したい。
2025年7月作成
取材日:2025年3月28日(金)
審J 2507107
【参考資料】
1) 厚生労働省: 政策レポート 臓器移植法の改正内容. https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/01/01.html (最終アクセス:2025年5月20日)
2) 肺および心肺移植研究会レジストリー: 2025年レジストリーレポ―ト. https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/registry/
(最終アクセス:2025年5月20日)
3) 肺移植関連学会協議会: 肺移植レシピエントの適応基準. https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/kanren/
(最終アクセス:2025年5月20日)
4) Leard LE et al.: J Heart Lung Transplant. 40:1349-79, 2021.
5) 日本臓器移植ネットワーク: https://www.jotnw.or.jp/
6) 日本臓器移植ネットワーク: 臓器ごとの移植事情.
https://www.jotnw.or.jp/learn/about/circumstances/ (最終アクセス:2025年5月23日)
7) 日本臓器移植ネットワーク: 臓器提供・移植データブック2017 第2章 肺移植登録者.
https://www.jotnw.or.jp/files/page/datas/databook/doc/02_lutx_waitinglist.pdf (最終アクセス:2025年5月23日)
8) Nakajima D et al.: J Thorac Dis 13:6594-601, 2021.
9) 伊藤洋至ら: 日臨床会誌 21:177-81, 2001. 10) Gochi F et al.: J Heart Lung Transplant. 40: 607-13, 2021.
11) Levin DJ et al.: J Heart Lung Transplant. 35: 397-406, 2016.
12) Courtwright A et al.: HLA 91: 102-22, 2018.
13) 日本移植学会: 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023. ぱーそん書房, 東京. 2023.
14) Wit CA et al.: J Heart Lung Transplant 32: 1034-40, 2013.
15) Otani S et al.: Transplant Immunology 31: 75-80, 2014.
16) 芳川豊史ら: 移植 56: 53-68, 2021.
17) Hachem RR et al.: J Heart Lung Transplant 29: 973-80, 2010.
18) Ius F et al.: Am J Transplant 18: 2295-304, 2018.
19) 中島大輔ら: 移植 58: 371-80, 2023.